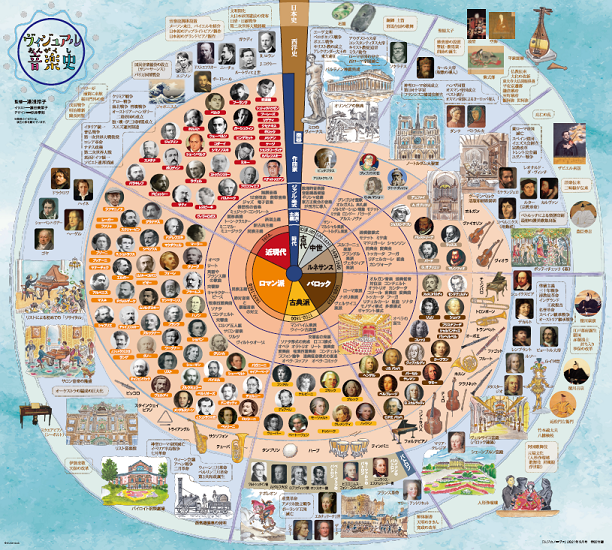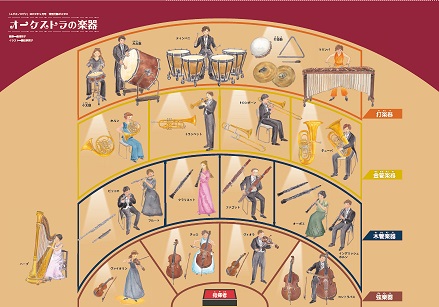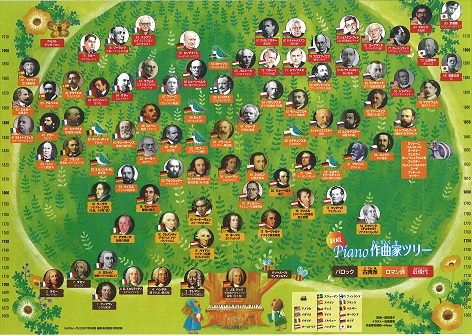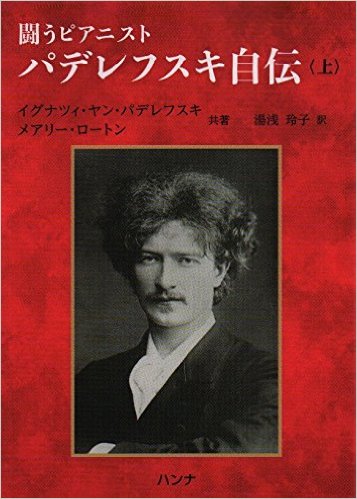ショパン:ピアノ・ソナタ 全3曲 楽曲分析 (2015年11月号)
第17回ショパンコンクールの開催に合わせ、ピアノ・ソナタ全3曲の楽曲分析を執筆しました。ショパンのソナタ第2、第3番の分析については5年前にも取り上げていますが、今回は7ページにわたるカラーページで、3曲の全楽章についての構造、その特徴について触れることができました。はじめに、「分析の前に」という項目で、どんなことに注目して分析していくとよいか、検証しています。
ショパン:ソナタ第2番、第3番 (2010年5月号)
特集「ショパンのソナタ 徹底分析!」で、ショパンの3曲のソナタについて歴史的評価や特徴についてまとめたあとで、第2番と第3番を分析しました。2曲とも、第1楽章の再現部で第1主題を再現させない、という面白い共通点があります。
ドビュッシー:月の光 (2008年4月号)
着想の源となったヴェルレーヌの詩集『艶やかな宴』の説明と、作品の完成に至るまでの過程を追いました。何度も改作を重ねていた「渾身の作」であることを強調しています。 分析では、「静」と「動」のそれぞれの楽節を、和音の動きなどを解説することによって対比させました。
ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー (2007年11月号)
ガーシュウィンの出世作となった名曲。その歴史的初演の様子や、後の編曲版の普及を紹介しつつ、分析。「8つのモチーフ」「長大なカデンツァ」というふたつの特徴を中心に書いています。
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ (2007年10月号)
宮廷舞曲「パヴァーヌ」の説明に加え、ポリフォニックな書法に着目しながら分析しました。
楽曲分析シリーズ「21世紀に弾きたい曲」
2001~2005年まで「ショパン」誌に掲載していた楽曲分析シリーズ。20曲のピアノ作品について、時代背景と解説、譜例付きの楽曲分析を執筆しました。
掲載曲:モーツァルト:きらきら星変奏曲、ドビュッシー:月の光、チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番、ショパン:ピアノ・ソナタ第3番など